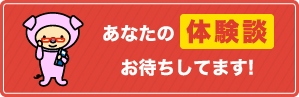【2025年】お年玉、何歳からあげる?金額の相場を年齢別に解説します!
更新日:
子育のこと

忙しいクリスマスに続く年末年始。
実家に帰ったり、親戚を迎えるために片付けや大掃除をしたり…本当に忙しい時期ですよね。
2025年、まもなく新しい年が始まります!
2024年は、物価高や「年収の壁」問題など家計を悩ませる話題が多かった一方、パリ五輪での日本選手の活躍や「金」が象徴する輝かしい出来事もありましたね。
「金」といえば…?
お正月に避けて通れないのが「お年玉」の準備。
いくらくらいあげればいいのか、あるいはいつまであげればいいのか…悩むことも多いはず。
そこで今回は、次の2つに注目してみました!
・お年玉の金額相場
・決めておくと便利なお年玉ルール
どうしようか迷っている方のヒントになれば幸いです♪
お年玉の金額相場って、いくらくらい?
金額を決めるのは子どもの年齢が基準になることがほとんどです。早速お年玉の金額相場を年齢別にみていきましょう!
乳幼児~小学校入学前(0~5歳)
金額の相場…0~1,000円
傾向として0~2歳くらいの場合はお年玉を渡さないという人も多いようです。
まだまだお金の価値自体がわからないので、お金ではなくおもちゃやお菓子、絵本などをプレゼントする方もいます。
一方で自分の子どもがお年玉を昔にもらっていた場合には、同程度の金額を渡しておくのが無難といえるでしょう。
3~5歳になると、おままごとなどを通じてお金の価値が少しづつわかるようになってきます。
500円玉~1,000円程度を渡すと、お使いも兼ねて自分の好きなものを買うという経験ができます。
お札よりも硬貨をのほうがわかりやすいのか、ポチ袋から500円玉が出てきて大歓喜!!という話もききますね。
小学校1~6年生(6~12歳)
金額の相場…1,000~3,000円
小学校に上がるとほとんどの子がお年玉をもらっています。
数の概念が理解できるようになってくるため、硬貨よりも紙幣が入っている方が喜びも大きいようです。
低学年のころは、1,000~2,000円でも十分でしょう。
3年生以上になってくるといくら貯めて何を買うという計画を立てるようになってくるので3,000円程度渡すことも増えてくるようです。
中学生(13歳~15歳)
金額の相場…3,000円~5,000円
お金を使う計画がより具体的になってくる時期です。
お年玉もある程度自由に使えるようになり、買いたい物に対してどれくらい貯めれば良いのか考え始めます。
友達と出かけるための費用にあてたり、ゲームや本など買いたいものも高額になってきます。
半分は使って半分は貯金のために親が預かる、という家庭も多くなります。
高校生(16歳~18歳)
金額の相場…5,000円~10,000円
高校生になると、お金を使う計画だけでなく、自分で管理する能力もある程度備わってきます。
さすがに小学生と同程度の金額とはいかないため、金額は大きくなりがちです。
学校の許可さえあればアルバイトもできる年齢になるので、渡す金額も一概に決めることは難しいです。
家庭の考え方や状況に応じて決めていきましょう。
大学生や社会人(18歳~)
金額の相場…5,000円~10,000円
お年玉は高校生でおしまいという家庭も一定数あるようです。
一方で学生のうちはお年玉をあげると決めている家庭もあることから、高校卒業、成人、大学卒業がお年玉のおわりタイミングにもなります。
自分で収入を得られるようになると、受け取る子どもたちももうお年玉をもらう年齢ではないから…とあまり期待していないことも。

決めておくと便利なお年玉ルール
自分の子どもに渡すお年玉であれば、金額もタイミングも教育方針次第なので悩む必要がありません。
しかし、甥や姪、孫に渡すときは頭を悩ましてしまう人もいるでしょう。
渡した金額は親に伝わるものですし、子ども同士で「お年玉、いくらだった!」と無邪気に話してしまうこともあるでしょう。
貰った子の間で不公平さが出てしまわないように、気を配る必要もあります。
筆者の親戚内では、一番最初の子どもが生まれたタイミングで姑&嫁たちでお年玉会議を開催して、ルールをざっくりと決めました。
甥・姪のお年玉スタートは小学生にあがってから、小学校の間は一律3000円、中学生は5000円、高校生以上は10,000円、18歳の成人のタイミングでお年玉終了です。
また、編集部員の中には
・年齢×500円と決まっていた
・毎年1000円ずつ増える仕組みだった
と決めていた家庭もありました。
ルールを先に決めておくと、甥・姪にお年玉をいくらあげたほうがいいのかと悩む事もなく、家計簿をつけていても「来年はこのくらいかかるからとっておこう」と予測もできて安心です。
また、子どもたちは、お年玉をいくらもらったかで喧嘩になってしまうこともあります。
「〇年生だから〇円なんだよ、大きくなったら〇円もらえるよ」ということを理解してもらえるので、おすすめです。

もらったお年玉はどうする?子どもたちの使い道No.1は「貯金」
貰ったお年玉をどう扱うかも頭を悩ませる1つのことです。
多くの親は「一部を使わせて、残りは貯金をしておく」ようです。
ネットのアンケートなどを見てみると、お年玉の使い道堂々1位は
「貯金」!
なんとも大人びた回答となりました。子ども自ら「貯金しておいて」と言ってくるケースも少なくないようです。
しかし、貯金をしておくだけだと出てくるデメリットもあります。
1つは、お金を使って失敗をする経験がもてないことです。幼い頃に失敗することで学べるお金の気づきもあるでしょう。
お年玉の活用術については、こちらにもまとめています。
まとめ
お年玉は準備する側にとって、「いくらにしよう」「いつまであげよう」「ほかの家は…?」と悩みの種になりがちです。
それでもお年玉をもらう子どもたちの嬉しそうな顔や、それを使うことで得られる学びもあります。
お年玉は本来子どもの成長を祝い、子どものために渡すものです。
新年のタイミングで、気持ちよくお祝いとして渡せるようにしたいですね。
しゅふJOBで「家庭と両立がしやすい」お仕事を見てみる