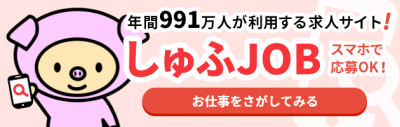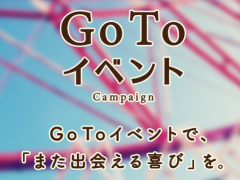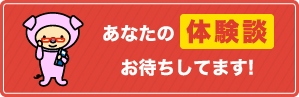特別定額給付金(10万円給付)はいつもらえる?申請方法・世帯主の確認方法は?
更新日:
お金のこと

新型コロナウイルスの感染拡大により、休校・休業の措置が取られるなか、政府は緊急経済対策として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円を支給する、と発表しました。
「10万円はどうやったら受け取れるの?手続きが必要?」
「世帯主って…パパで合ってる?一人暮らし中の子どもは?…どうやって確認したらいいの?」
と気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、特別定額給付金について、申請方法やしておくべき事前準備についてご紹介します。
▶PCサイトはこちらから
特別定額給付金とは?
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、令和2年4月20日に閣議決定されました。感染拡大の防止にとりくみつつ、家計への支援を行うために実施されることになった支援制度です。
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)
実施主体:市区町村(経費は100%国が補助)
給付対象者:令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されているもの
受給権者:住民基本台帳に記録されている者が属する世帯の世帯主
給付額:対象者1人につき10万円
とされています。
※特別定額給付金の基準日が4月27日のため、28日以降に生まれた子どもについて支給対象外になっています。ただし、全国で30以上の自治体(市町村)が独自の支援を行っています(大阪府河内長野市、岡山県浅口市、愛知県田原市など)。お住まいの市町村で対象になるか確認をしてみてください。

申請はどうやったらいい?
感染症拡大防止の観点から、窓口申請ではなく、郵送申請もしくはオンライン申請となっています。
1.郵送申請
市区町村から、受給権者(世帯主)あてに申請書が郵送されます。
申請書に振込先口座を記入して、振込先口座の確認書類と、本人確認書類の写しを同封し、市区町村に郵送します。
申請書のみほんはこちら。申請書はこちらからもダウンロードが可能です。総務省 特別定額給付金_郵便で申請する
※コンビニコピー機での免許証コピーのやり方は下記にまとめています。
2.オンライン申請
マイナンバーカードの所持が必要です。
マイナポータルから、振込先口座を入力します。振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名)で本人確認を実施します。
※オンライン申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
・マイナポータルの検索orアプリのインストール
・マイナンバーカード受け取り時に設定した英数字6~16桁の暗証番号
・振込先口座の確認書類
※電子申請(電子署名)に対応しているスマートフォンかどうか確認ください。iphoneの場合、iphone7~iphone11pro、Androidの場合、AQUOS、Pixel、Xperia、arrowsなどが対象になります。対象機種の一覧はこちらから
マイナンバー申請についてはこちらから
いつ支給される?手続きはいつまで?
「市区町村において決定する」とされており、既に市区町村によっては支給が始まっています。
申請期限は、郵送申請の受付開始から3か月以内です。
申請状況・支払い状況の確認をするには?
オンライン申請(マイナンバーカードを利用したマイナポータルからの申請)の場合、オンライン申請時にメールアドレスを入力しておくと、申請完了の通知を受け取ることができます。
その後の振込対応状況については、申請先の市区町村に確認することになります。振込完了の連絡は行っていない自治体が多いようです。
振込完了の確認について、私事ですが、振込先に指定した口座アプリを使用し「振り込み」「支払い」のたびに通知が届くようにしているので、支給にすぐ気づくことができました。もしご利用の金融機関アプリを使用されている方は、通知設定をしてみても良いかもしれません。
各都道府県の新型コロナウイルス感染症対策ページ、各都道府県知事の会見ページを一覧で見ることができます。下記記事もご活用ください。
参考:総務省 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
参考:マイナポータル
▶PCサイトはこちらから
世帯主とは…一人暮らしの場合は?
受給権者:住民基本台帳に記録されている者が属する世帯の世帯主
受給権者は「住民基本台帳に記載されているものが属する世帯の世帯主」となっています。
「遠方に住んでいる娘・息子は一人暮らしだから、別世帯になるのかしら…?」
「単身赴任中の夫とは別の家に住んでいるけど、世帯主は夫?私?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
”世帯”の定義は、国・機関によりさまざまです。ひとつの国の中でも、統計調査の目的によって世帯の定義が見直されることもあるほど、カチッと決まっているものではありません。
日本では”世帯の生計を維持する主たる者=世帯主”とされています。
そのため、一人暮らしであっても”独立した住居”で”独立した生計を営んでいる”=独居世帯として、世帯主と考えられます。
たとえば、全く収入がなく実家からの仕送りだけで一人暮らしをしている学生であっても、独立した住居に住んでいる手続きを済ませていれば、別世帯とみなされて世帯主となります。
住民票が基準となって決まっているので、住民票の手続きを行っていた場合、書類上に世帯主の氏名が記載されます。
世帯主とは…同棲、事実婚の場合は?
世帯主は、1世帯に1人でなくても問題はありません。
例えば、同棲や事実婚、婚姻している夫婦でも「夫婦で生計と共にしているけれど、お互い独立した収入があり、それぞれ世帯主となりたい」場合は、世帯主が2人いる世帯、ともできます。
世帯主を増やしたい、世帯主を変更したい場合は、世帯主変更届を役所に提出することで変更ができます。
住民基本台帳と世帯主の確認方法
今回の受給については「住民基本台帳に記載されている者が属する…」となっていますね。
住民基本台帳とは、氏名・生年月日・性別・住所が記載された住民票を編成したものです。
・選挙名簿の登録
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の、資格の確認
・児童手当の受給資格確認
・生活保護および予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務
などの事務処理のために使われています。確定申告や年末調整に必要な書類を記入するときにも必要になります。
世帯主の簡単な確認方法は、住民票を確認すること。住民票の世帯主の欄に、世帯主の氏名が記載されていますよ。
マイナンバーカードの申請方法を知ろう!
さて、オンライン申請の方法を確認して、マイナンバーカードの申請がまだだった…!と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の給付について、申請のタイミングによっては間に合わない可能性があります。郵送手続きを検討したほうが良いこともあるので、お気を付けください。
特に、申請手続きからカード発行までに1~2か月かかってしまうこと、カードをもらうために窓口に行かねばならないため外出が必要になることは留意しておかねばなりません。
「今後のためにマイナンバーカードを作っておきたい」と思った方むけに、マイナンバーカードの申請方法をまとめました。一緒に確認していきましょう。
※通知カード・個人番号カードが必要です。通知カード・個人番号カードを紛失した/心当たりのない方はこちら(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの発行申請には「4種類の方法」があります。
1.郵送による申請
2.スマートフォンによる申請
3.パソコンによる申請
4.まちなかの証明写真機からの申請
それぞれ確認していきましょう。
1.郵送による申請
マイナンバーカード交付申請書に顔写真を貼り、記入・押印し、送付用封筒に入れて郵便ポストへ投函します。
住民票の住所に「通知カード」と一緒に、交付申請書が届いているので、切り離して使用することができます。
もし、交付申請書をなくしてしまっても大丈夫。マイナンバー総合サイトから申請書のダウンロードができます(こちらから)。送付用の封筒も印刷できるので、そちらを使えば送料もかかりません。
2.スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影します。
交付申請書のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。
メールアドレス、メール連絡用氏名、申請書ID(半角数字23桁)を入力します。
※QRコードを読み込んだ場合申請書IDは自動で入力され変更できないようになっています。
所定のフォームに生年月日、電子証明書の発行希望有無、氏名の点字表記希望有無を入力し、顔写真を添付して、申請します。
登録したメールアドレスあてに申請完了のメールが届いたら、申請完了です。
3.パソコンによる申請
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請します。
交付申請用のWEBサイトにアクセスして、画面に表示される必要事項を入力します。顔写真を添付して、送信します。
※交付申請書に記載されているID(半角数字23桁)が必要です。
4.まちなかの証明写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明写真機で顔写真を撮影して申請します。
申請に対応している写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択します。
撮影用のお金をいれて、交付申請書に記載されているQRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内に従って必要事項を入力し、写真を撮影して、送信します。
マイナンバーカードの受け取り方法
原則、お住まいの市区町村の役所窓口で、カード受け取りになります。
申請が完了したら、約1か月後に、お住まいの市区町村から交付通知書が送付されます。
通知書に記載された交付場所に、交付通知書、通知カード、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持参して本人確認ができると、カードを受け取ることができます。
マイナンバー「通知カード」は5月25日で廃止?!
紙製の「通知カード」が5月25日に廃止されることはご存じでしょうか。
”廃止”されると、通知カードでもできていた以下の2点ができなくなります。
・通知カードの新規発行・再交付
・通知カードの住所や氏名などの記載変更
ただし、通知カードに記載された氏名、生年月日、住所に変更がない場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き通知カードを使うことはできます。
でも、住所が変わるかも…?!という方は早めに手続きをしておきましょう。住所が変わってしまえば、通知カード=マイナンバーを証明する書類ではなくなってしまうのです。マイナンバーカードの発行手続きは5月25日以降でも行えます。
マイナンバーカードが発行できていないけれど住所が変わってしまう場合、マイナンバーを証明する書類として「住民票の写し(住民票記載事項証明書)」を提示することになります。
参考:通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!
まとめ
特別定額給付金の給付は決まったものの、支給時期は市区町村によります。すでに申請の受付開始日について公表が始まっている市区町村もあります。お住まいの市区町村HPを確認してみてください。
感染拡大の防止にとりくみつつ家計への支援を行うために実施されることになった、この支援制度。各家庭ではどのように使用するのでしょうか。アンケートを行ったところ、約7割の人が「生活費にあてる」としています。アンケート結果はこちらからご覧いただけます。
家庭や子どもの事情でお休み相談OK!お仕事を見てみる|しゅふJOB