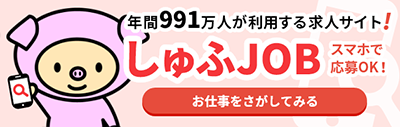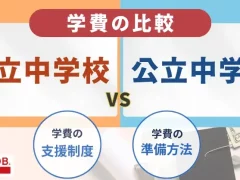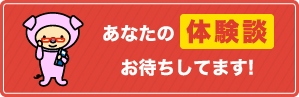「保育園の洗礼」を乗り越える!保護者が知っておきたい実践的対策とは?
公開日:
子育のこと

保育園に子供が通い始めると必ず通るといわれているのが「保育園の洗礼」。
「復職したと思ったら、連日保育園からのお迎え要請が続いてモヤモヤ…」
「治った!と思ったらまたすぐ鼻水がじゅるじゅる、咳もゴホゴホ…いったいどうしたらいいの?」
働くママ・パパには仕事や職場に影響が出る深刻な悩みですよね。
今回は、保育園の洗礼とは?その対策方法についてご紹介していきます。
▶お迎え要請も怖くない!ママ・パパ歓迎のお仕事探しなら『しゅふJOB』★
もくじ
保育園の洗礼とは?
保育園は0歳~小学校入学前までの子供たちが集団生活をしています。
年齢や人数によってクラスが分けられているものの、園庭で同じ道具を使って遊んだり、早朝や延長保育では1つのクラスに集まって過ごすことも多くあります。
そのため、免疫ができていない菌やウイルスをもらいやすく、感染症が流行する季節にはクラスを問わず保育園全体で感染者が出やすくなります。
特に免疫力が少ないのが入園して間もない時期。
さまざまな風邪や感染症に出会うため、入園後の短期間で早退やお休みを繰り返すことになり、これが「保育園の洗礼」と呼ばれています。
保育園の洗礼、どんな症状が出る?
多くは風邪のような症状から始まっています。具体的には
・発熱
37.5度以上の熱がある場合
・鼻水
透明な鼻水はウイルスが入ってきた初期症状とされています。黄色や白の鼻水は風邪ウイルスと戦っている最中です。
・咳
大人に比べ鼻孔や気道が細いので、風邪などで少しでも粘膜が腫れると息苦しくなります。
・嘔吐
胃腸炎が流行っている場合、家族に広がる可能性があるので要注意です。
・下痢
風邪の症状でもお腹が緩くなってしまいます。
・発疹
ぽつぽつが出てきただけでもお迎え対象になることがあります。虫刺されやかぶれなどのこともありますが、水疱瘡やはしか、とびひなどが疑われる場合病院に連れていく必要があるためです。
鼻水や咳だけでお迎え要請や登園不可になることはありませんが、発熱に繋がることが見込まれるのでできるだけ早めに対処を考えていきましょう。
嘔吐下痢は感染性が高いため、厚生労働省では2回以上の嘔吐下痢があった日の翌日の登園は控えるようにとしています。
特に保育園では救急処置ができないため、急激に熱が上がった(熱性けいれんが起きる可能性がある)場合や、感染性の症状がある場合などは保護者に速やかに連絡をすることになっています。
保育園の洗礼はいつまで続く?
働くママ・パパが一番気になるのは「連日のお迎え要請はいつまで続くの?!」ということではないでしょうか。
保育園入園前にどれだけ免疫がついているか、入園してからどれだけ新しい菌やウイルスに出会ったか、子どもによってさまざまです。
多くの子は3~6か月ほどで落ち着いて登園できる日が増えるようです。
ただし、半年かかったという家庭もあれば落ち着くまで1年以上かかったという家庭もあります。
保育園に通い始めたばかりの子は、みんな免疫獲得のために頑張ってる!と思うしかないかもしれません。
いつから登園させていい?
熱は下がったけど鼻水や咳、下痢が続いている場合に登園させていいものか迷う方も多いのではないでしょうか。
保育園では預かりのルールが決まっていることが多いので、入園のしおりや、保育室からのおたよりを確認してみましょう。
感染症だった場合、自治体の方針にもよりますが多くは「解熱した次の日から3日間は出席停止」となっています。
たとえば月曜日に熱が収まってきたら火曜・水曜・木曜の3日間はお休みして、金曜日から登園可能になります。
インフルエンザの場合は発症した日から5日間治療となっているので、月曜日にインフルエンザの症状(発熱など)が出たら火・水・木・金は登園できません。
厚生労働省では38度以上の発熱があった場合翌日の登園を控えるように呼び掛けています。
熱が38度から下がってから、24時間経ちふつうの体調に戻ったことが確認できてから登園させましょう。

発熱が落ち着いても登園は控えた方が良い?
当然のことながら、保育園の基準は各園によって様々ですので通っている園に直接方針を確認することをおすすめします。
但し、下記の登園基準を子供がクリアしていれば登園しても良いでしょう。
【保育園の登園基準】
・24時間以内に38℃以上の熱が出た場合、登園を控えるのが望ましい
・37.5℃以上の熱があれば、欠席するように定めている保育園・幼稚園もある
・37.5度以下の場合でも平熱より高かったり、鼻水や咳など他の症状が出たりしている場合は念のためお休みさせたほうが安心
【登園再開の目安】
・解熱後24時間経過してから登園することをおすすめする
・発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれる状態である場合
但し、先述の通り年齢は問わず多くの子供が生活する保育園では、免疫ができていない菌やウイルスを貰いやすいため、短期間で早退・お休みを繰り返す可能性が高いです。
したがって、ご自身の子供の体調が回復しても油断せず登校再開の目処を伺うのが良いでしょう。
保育園の洗礼を受けたら?
保育園に通い始めて発熱や咳、鼻水の症状が出始めたらどうしたらいいのでしょうか。
まずは病院に行って診察を受けましょう。かかりつけの小児科、耳鼻咽喉科をつくっておきましょう。
もし当てがない場合は、保育園や幼稚園の健康診断などで提携している病院がないか保育園に確認してみてもいいでしょう。
鼻水が出ている場合は中耳炎にも注意しておきましょう。鼻・目・耳・喉はつながっています。
たかが鼻水と思わずに、より深刻な症状に繋がる前に対処しておきましょう。
早い回復を促す4つの方法
子どもが体調を崩してしまったら、できるだけ早く回復してほしいですよね。
早い回復を促す4つの方法をご紹介します。
1.早めに病院に行く
症状が出始めたら早めの対策が肝心です。早めに病院に連れていきましょう。
ただし、感染症かどうかの検査は発熱してからある程度時間が経たないとはっきりした結果がわからないことがあります。
高熱が出ている場合、2日連続で病院に行くこともあるので留意しておきましょう。
また、重症化してしまったり、治療が必要な状態になってしまうこともあります(喘息や、尿路感染など)。
熱が引いたから治ったと安易に判断せず、追加の治療が必要ないか医師に診てもらうようにしましょう。
2.鼻水をこまめに取り除く
吸っても吸っても出てくる鼻水を取り除くのは大変ですが、放っておくともっと大変なことに!
喉に流れて喉が痛くなりご機嫌が悪くなったり、痰が絡んだ咳になったり、呼吸が苦しくなって夜寝つけず寝不足になってしまうこともあります。
耳のほうに影響が出ると中耳炎になってしまったり、目のほうに影響がでると結膜炎になってしまうこともあります。
電動吸引機やポンプ式吸引機を使うと便利です。
3.たくさん寝かせてあげる
体調が悪い時は寝苦しくて寝不足になってしまう子どもがたくさんいます。
お昼寝の時間以外でも、眠そうにしていたらたくさん寝かせてあげましょう。
鼻水が多いときは呼吸がしやすいように、頭や肩が胸より少し上がるように角度をつけてあげると楽になります。
ただし、柔らかすぎるタオルを頭の下に敷くと寝返りができない子は呼吸ができなくなってしまうこともあるため気を付けてください。
子どもの発熱は熱性けいれんにも気を付けなくてはいけません。
熱が一気に上がるタイミングでけいれんが起きるため、短時間で熱が上がった時は早めに連絡を入れる保育園がほとんどです。
4.給水はこまめに
乳幼児は体内の水分が多く、1日にたくさんの水分を必要としています。
発熱による汗や嘔吐下痢、鼻水、咳で水分が多く出て行ってしまうので脱水症状になりやすいのです。
こまめに水分補給ができるようにサポートしてあげましょう。

保育園の洗礼を防ぎたい!家庭でできる対策
帰宅後は手洗い・足洗い
まずは基本の手洗いをしましょう。石鹸を使ってきれいに洗い流します。
保育園は裸足で過ごすことが多いので、足にも菌がついています。靴下をはいていても脱がせて足を洗ってあげます。
できればすぐにお風呂に入り、髪や顔についたウィルスも流してあげると安心です。
帰宅後すぐにご飯にしたくなるものですが、手足についた菌も一緒に食べてしまう可能性があるので、まずは菌を落とすことから始めましょう。
鼻水をこまめに取り除く
電動で鼻水が吸える機械や、圧縮ポンプで鼻水を取るものも販売しています。
口で吸うものも安く手に入りますが「親が最近を吸って感染してしまうから使い方が難しい」という声もありました。
また、お風呂上りに体があたたまって鼻水がゆるむので除去しやすくなります。
少しかわいそうかもしれませんが、大泣きをした後は体温が上がって鼻水が緩んでいることが多いので、泣いた=鼻水除去チャンスと思ってもいいかもしれません。
また、基本的なことですが、バランスのとれた食事を意識しましょう。
朝ごはんを抜かず1日3食食べる、緑黄色野菜を多めにとるなどできるところから始めていきましょう。
入園前にできる準備
これから産休・育休から復職する人は、保育園入園前にできる準備をしておきましょう!
かかりつけの病院をつくっておこう
かかりつけの病院をいくつか作っておきましょう。
まずは小児科、土日や夜間に子どもが診療を受けられる病院、耳鼻科、皮膚科は必須です。
特に土日や夜間の外来は小児科医がいないため対応ができない病院も多いので、事前に調べておくことでもしもの時にも安心できます。
ママ・パパがすぐ電話できるように、携帯電話に登録したり、いつでも見られるところに書いて貼っておくのも安心です。
また、以下を連絡先に登録しておきましょう。
#8000 こども医療でんわ相談
休日・夜間のこどもの症状にどう対処するか、病院に連れて行ったほうがいいか相談をすることができます。
ここに電話をすると居住している都道府県の相談窓口に自動転送されるので、近くで診察が受けられる病院を教えてもらえることもありますよ。
※詳しくはこちら
#7119 救急安心センター
急な怪我や病気をして救急車を呼ぶか迷った時に専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口です。
※詳しくはこちら
保育園入園前に予防接種(定期接種・任意接種)を検討しよう
保育園での集団生活において、ある程度の感染症にかかることは仕方ありませんし、それが「洗礼」と呼ばれる理由でもあるでしょう。事実、何度も軽い感染症にかかるうちに自然に免疫がつき、抵抗力の高まりとともに徐々に感染症にかかりにくくなっていきます。
しかし、幼児期にかかる恐れのある感染症の中には、命に危険を及ぼすものや後遺症に苦しむものもあり、それらにかかることは絶対に避けたいものです。
そのため、保育園入園前や入園後すぐにワクチン接種を検討することをおすすめします。ワクチン接種には、感染症の予防や重症化を防ぐ目的があり、日本小児学会も接種を推奨しているものがあります。以下では、予防接種の種類と対象となる病気について解説します。
予防接種には「定期接種」と「任意接種」の2種類があり、それぞれに特徴があるため、両者の違いを押さえておきましょう。
1.定期接種とは
定期接種は法律で定められた予防接種で、市区町村などの自治体が行っています。実施は公費でまかなわれるため基本的に無料ですが、一部で自己負担が発生する場合もあるため注意が必要です。定期接種が受けられるワクチンは以下の通りです。
・ロタウイルスワクチン:ロタウイルスによる重度の胃腸炎を予防する
・Hib(ヒブ)ワクチン:細菌性髄膜炎や喉頭蓋炎などの感染症を予防する
・小児用肺炎球菌ワクチン:肺炎球菌による感染症(細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎など)を予防する
・4種混合ワクチン:ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオに対する予防
・BCG:結核の予防
・B型肝炎ワクチン:B型肝炎を予防する
・MR(麻疹風疹混合)ワクチン:麻疹と風疹を予防する
・水痘(水ぼうそう)ワクチン:水ぼうそうを予防する
・日本脳炎ワクチン:日本脳炎を予防する
上記の感染症は子どもの命に危険を及ぼす可能性があるため、国や自治体が接種スケジュールを組み、接種することが強く推奨されています。
定期接種の重要性を理解し、適切な時期に接種するよう十分に注意しましょう。
2.任意接種とは
任意接種は、保護者の判断により受けられる予防接種で、接種義務があるわけではないので原則的に自己負担ですが、自治体によっては一部や全額を負担してくれる場合もあります。
任意接種の代表的なものは下記の通りです。
・おたふくかぜワクチン:流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)を予防する
・インフルエンザワクチン:インフルエンザを予防する
予防接種を受けることにより、子どもが重大な感染症にかかることを防げるだけでなく、家庭や保育園での集団感染予防にも繋がります。具体的な接種スケジュールについては、事前にかかりつけのお医者様やお住まいの自治体に確認してみましょう。
保育園入園前後に受けるワクチンまとめ
| ワクチン種類 | 推奨接種開始年齢 | 回数 | 備考 |
| ロタウイルス | 生後2か月 | 1価:2回 5価:3回 |
ロタウイルスによる胃腸炎と重症化の予防 |
| Hib(ヒブ) | 生後2か月 | 4回 | Hib(ヒブ)による細菌性髄膜炎や喉頭蓋炎、肺炎などを予防 |
| 小児用肺炎球菌 | 生後2〜7か月 | 4回 | 肺炎球菌による細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎などを予防 |
| 4種混合 | 生後2か月 | 4回 | ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオを予防 |
| BCG | 生後5〜8か月 | 1回 | 結核の予防 |
| B型肝炎 | 生後2か月 | 3回 | B型肝炎の予防、B型肝炎の母子感染予防 |
| MR(麻疹風疹混合) | 1〜2歳未満 | 2回 | 麻疹(はしか)、風疹を予防 |
| 水痘(水ぼうそう) | 生後12〜15か月未満 | 2回 | 水ぼうそうを予防 |
| 日本脳炎 | 3〜4歳 | 4回 | 日本脳炎を予防 |
| おたふくかぜ | 1歳 | 2回 | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)を予防 |
| インフルエンザ | 生後6か月〜12歳 | 毎年 | インフルエンザを予防 |

病児保育・病後児保育を活用しよう
働くママ・パパの頭を悩ませるのは、病気の子供が家にいるから仕事にならない、どうしても外せない仕事があって看病の手・目が足りない…というところです。
お住まいの自治体で病児保育・病後児保育のサービスがあるか確認しておきましょう。事前登録ができるところは事前に申し込みをしておくと安心です。
ただし自治体主体の病児保育は受け入れ可能人数が少なくいつも満床で預けられない!という声も聞こえてきます。
病後児を見てくれる民間サービスも調べておくと安心です。
冬は毎年要注意!感染症シーズン本番の到来
保育園の洗礼が終わったからといって、安心はできません。
大人も毎年「インフルエンザに罹りました…」という人が増える冬は、子どもたちにとっては最も感染症にかかりやすいシーズンの到来です。
インフルエンザ、RSウイルス、溶連菌、胃腸炎など、感染性の病気が流行します。
インフルエンザは11月頃から小児科で予防接種の予約が始まるので、スケジュールを確認しておくことをおすすめします。
ちなみに夏はプール熱、手足口病、ヘルパンギーナ、食中毒などが流行しやすいと言われています。
2023年5月から、ヘルパンギーナが大流行しています。
ヘルパンギーナは主に0~4歳が中心に感染拡大をするウイルス性の感染症ですが、大人にも感染します。大人が罹患した場合、子どもよりも症状がひどいことがほとんどです。
保育園はどのくらい休んだらいい?仕事はどうしたらいい?というパパ・ママの疑問をこちらにもまとめています。
影響が少ない働き方はある?休みの取り方は?
使える「休暇制度」を知っておく
休む=有給休暇を使うと思いがちですが、ほかにも使える休暇がないか確認しておきましょう。
有給休暇がたっぷり残っている人でも「20日くらいあったが半年もたないで使い切ってしまった」という声は少なくありません。
「子の看護休暇」という年間5日子どもの看護のために休暇を取得できる制度があります。国の制度なので「私の職場では取得ができない」ということはありません。使用方法を勤務先の人事労務に確認しておきましょう。
2023年4月には育児・介護休業法が改正されています。以下の記事で詳しく説明していますので、こちらも併せて読んでみてください。
職場で協力体制を作っておく
保育園に入園したての子どもが病気をもらってきやすいことは、昨今のママ・パパにとっては常識になってきていますよね。
それでも突発の休みは同僚も困ってしまうものです。できるだけ日頃から仕事を共有しておきブラックボックス化を避けましょう。
自分以外の人が対応できるよう資料を共有の場に格納したり、こまめに報連相をしておくことも大切です。
これから仕事を探すママ・パパができる対策として、夫婦で休みの日をずらせるようにしておくという手もあります。
例えばママが土日祝休みでパパが平日休みであれば、子どもが感染症で連日自宅にいることになってもカバーしやすくなります。
子どもと休みを合わせたい場合は、シフト制の職場を選ぶのもひとつの手でしょう。
どうしても職場の理解がない場合、転職を視野に入れることも考えましょう。
主婦・主夫歓迎の求人を多く扱うサイト『しゅふJOB』では家庭や子供の都合でお休み相談ができる職場もたくさん掲載されています。
ほかにも、短時間で働きたい人向けの求人サイトや、ママの転職に特化したエージェントも存在しています。まずは情報収集を始めてみましょう。

保育園の洗礼がつらい…乗り切ったママ・パパたちの体験談
最後に、保育園の洗礼を受けても少し明るく前向きな気持ちになれる(なれそうな)ママ・パパたちの実体験をご紹介します。
・新しい免疫獲得!と思っている。何度も発熱を繰り返すので心が折れそうになるが、成長のためなら気持ちよく応援できると思うから。
・感染症になったら割り切って、子どもと過ごす時間が増えたと考えている。反対に、仕事に行ける日は貴重な時間だと気づいたので、とにかく頑張って仕事をしています。
・あまりに何度も熱が出るので、保育園や病院から「子どもをちゃんと見ていないと思われるんじゃないか」と不安だった。担任の先生に思い切って打ち明けてみたら、何度もお熱を出したりして強くなっていくから大丈夫!みんなそうですよ!と言われて心強かった。病院の先生からも「お母さんが頑張っても、もらってくるものはもらってくる!そういう時期だから、心配しすぎないで様子を見てあげて。気になることがあったらいつでも見せに来て!」と言われた。
・帰宅してから手洗い&足洗いをするようになったら、悪化する頻度が減った!最初は眉唾だと思っていたけど、うちは効果があったので試してみてほしい。
・娘がとびひになってしまい感染症で3週間くらい登園できなかった。本人はとっても元気なので家の中で走り回るし、オンライン会議にも顔を出してしまうし…今となっては思い出だけど、当時は本当にものすごく大変だった。同僚の子どもが洗礼を受けても、そういうものだからと思ってサポートをしている。
・熱が引いて治った!と思って念のため登園前に病院に連れて行ったら、中耳炎になっていた。本人は元気なので、家で仕事をしていても遊んで欲しがって仕事にならず…夫と交代で休みを取った。もっと大きな病気やケガをしたらこんな短い期間じゃなくなるはずなので、予行練習の気持ちで乗り切った。

今回は、保育園の洗礼についてご紹介しました。
子どもは集団生活の中で新しい知識や経験をしますが、その中にはウィルスや菌との出会いもついてきてしまいます。
できるだけ予防や対策準備をしながら、子どもたちの成長を見守っていきましょう。
また、感染源は保育園とは限らず、自宅に親が持って帰ってきていたり、久しぶりに会った親戚からもらってしまう可能性もあります。
共用部分(トイレや手洗い場、ドアノブ、手すり、照明のボタンなど)は水拭きをしてアルコール消毒をするなど、できるだけ子どもが過ごす部屋は清潔に、掃除や整理整頓を心掛けましょう。
季節にあわせた換気や加湿も大切です。加湿器は水を毎日交換し、エアコンも夏・冬前は特に掃除をしてから使いましょう。
ママ・パパ歓迎の職場を探すなら【しゅふJOB】!
参考