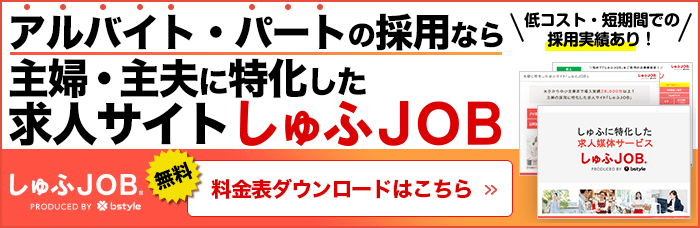法律関連
【社労士監修】短時間労働者とは?雇用・社会保険の加入条件まとめ
- 更新日:
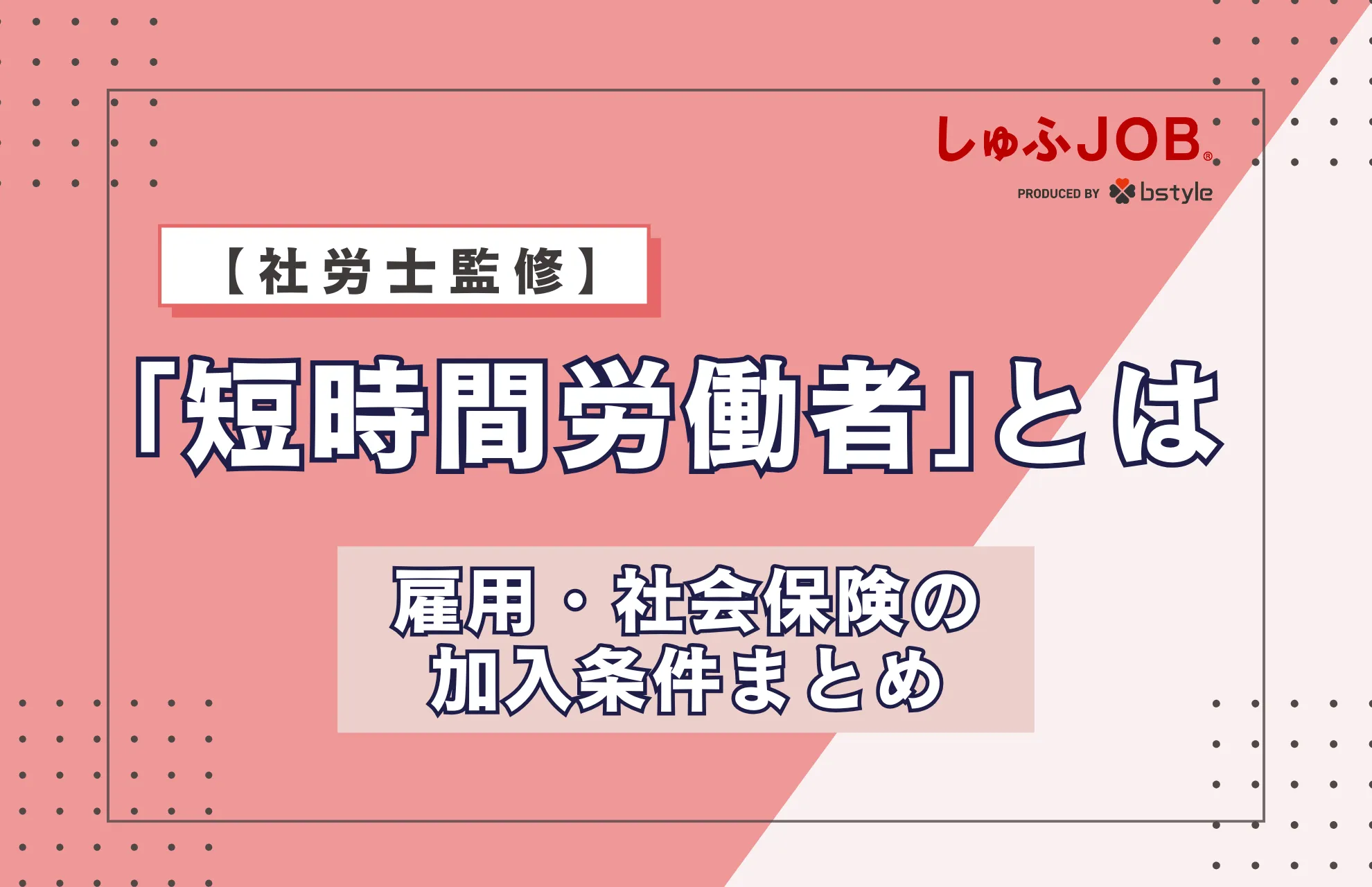
採用から雇用管理まで全部OK!
主婦・主夫のことならしゅふJOBにお任せください
年間1000万人以上が集まり、導入企業様数2万社以上の”主婦・主夫採用”に特化した
求人媒体しゅふJOB。
NHKをはじめ日経新聞、雑誌などにも多く取り上げていただき、
また革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞」において
「厚生労働大臣賞」を受賞しました。
しゅふJOBでは、プロのライターが求人原稿作成を無料支援。
人材に合った最適な求人原稿を、カンタンですぐに掲載できます。
また掲載課金だと1週間12,000円~で即採用も可能!
費用対効果が高くお客様にご好評いただいているプランになります。
<ご利用企業様のお声>
「応募数、求職者の就業意欲に満足!他媒体に比べ圧倒的に応募が多い」
「学生より主婦・主夫層の応募が欲しい、そんな時しゅふJOBが解決してくれた」
「法律関連の情報もすぐに発信してくれて助かる」
まずはお気軽にホームページをご覧ください。
監修
勝川 秀興氏 ( 勝川社会保険労務士事務所 代表 )
助成金活用を強みとし、設立以来2名から200名規模まで様々な業種の企業様へ、
助成金を徹底活用するためのコンサルティングや、株式会社ビースタイル メディア主催のセミナーなどで講師もしている。

この記事の監修者
石橋聖文
人気の記事
-

しゅふJOB・メソッド
求人募集しても人が来ない会社とは?3つの原因と応募を増やす方法を解説
求人を募集をしているのに人が来ない会社とは?採用担当者が気になる点ではないでしょうか。 求人広…
-
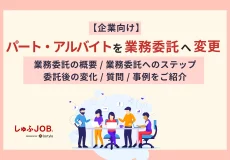
しゅふJOB・メソッド
【企業向け】パート・アルバイトを業務委託に変更した事例をご紹介
2020年は新型コロナ感染拡大を受け、昨今の「働き方改革」の推進以上に、大きく変化をもたらしました。…
-

しゅふJOB・メソッド
応募課金型の求人サイトとは?メリットやデメリットを事例を交えて解説
「できるだけ無駄な費用なく採用活動を進めたい」「応募がこなくて掲載料だけとられる状況に不満がある」と…
-

しゅふJOB・メソッド
ハローワークで応募が来ない!その原因と対策、成功ノウハウをご紹介
ハローワークは企業にとっては広告費がかからないため採用活動において強い味方です。 求職者が失業…
-

しゅふJOB・メソッド
しゅふJOB|企業様向け管理サイトのログイン方法
この記事ではしゅふJOB 管理サイトの具体的な活用方法を紹介いたします。 掲載4日で10名の応…
-

しゅふJOB・メソッド
テレアポ業務・カスタマーサポートセンターを完全リモート化!成功事例
新型コロナをきっかけに様々な業務のリモートワーク化が急速に進みました。ですがリモートワーク化が難しい…
-
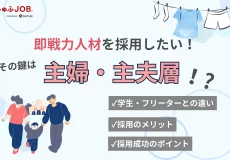
採用方法
即戦力人材の採用、その鍵は『主婦・主夫層』?│採用メリットを解説<パート・アルバイト>
パート・アルバイトで即戦力採用を行いたいが、売り手市場の昨今、自社が求める希望の人材からの応募を集め…
-

しゅふJOB・メソッド
新人研修も完全オンラインで!内容・メリット/デメリット・注意点は?参加した新入社員、上司の感想をご紹介します
2020年4月、求人サイト「しゅふJOB」運営元である、株式会社ビースタイルメディアには4名の新入社…
-

しゅふJOB・メソッド
検索ワード1位の「在宅」|勤怠の安定した在宅スタッフの活用術を解説
主婦/主夫採用に特化した求人媒体「しゅふJOB」のフリーワード検索の一位は常に「在宅」。 この…





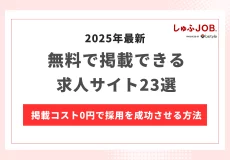
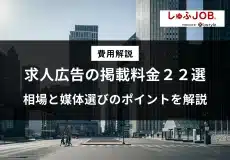
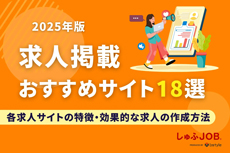
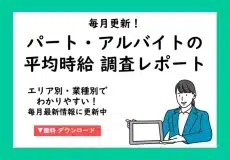
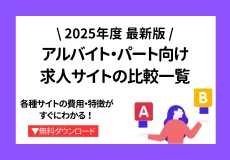
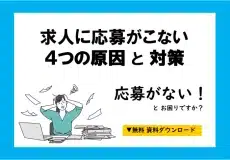

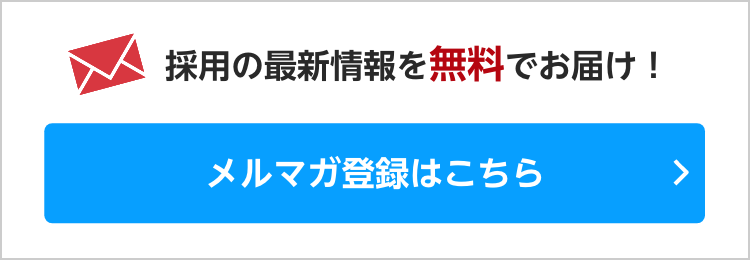
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者のことを表します。(主にパートやアルバイトを示す)
近年、短時間労働者の増加にともない、法律の見直し、特に「社会保険」の適用条件における法律の見直しが定期的に行われています。そのため、短時間労働者を雇用している、もしくは採用を検討している企業は、新しい法律に沿った対応や雇用管理が求められます。
この記事では、企業が短時間労働者を雇用するうえで必要となる基礎知識や、各社会保険の適用・加入条件をわかりやすく解説します。
掲載4日で10名の応募実績!求人サイト「しゅふJOB」の資料をダウンロードする
【目次】
パートタイム労働法とは何か
少子高齢化が進むとともに、労働力人口に占めるパートタイム労働者の割合は増加傾向にあります。そのような時流に合わせて、制度改正を重ねているのがパートタイム労働法です。
正式にはパートタイム・有期雇用労働法という法律について、本項では簡単に解説いたします。パートやアルバイトを雇用しようと考えている方には、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
2021年4月に全面施行されたパートタイム労働法
2018年7月に公布された働き方改革関連法の成立により、従来のパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正されました。
この法律は2020年4月より施行され、2021年4月には中小企業を含め全面的に施行されています。
2022年8月現在、働き方改革関連法は施行スケジュールの途上にあり、ひと通り施行が完了するのは2024年4月の予定です。
今後も働き方に関する法律は改正を重ねていくことが予想されるため、雇用側は法改正の動向に注目していく必要があるでしょう。
パートタイム労働法が施行される目的とは?
少子高齢化の進行に伴い、パートタイム労働者の中で女性や高齢者の占める割合が高まっています。その一方で、パートタイムや有期雇用で働く若年層や世帯主が増加する、というように働き方の多様化が急速に進んでいます。
しかし、パートや有期雇用労働者などの短時間労働者は、正社員との間に賃金や待遇の格差を感じています。そのような格差を是正し、労働者が持てる能力を正当に発揮できることを狙いとして、パートタイム労働法が整備されてきたのです。
賃金や待遇の不均衡に加え、短時間労働者が抱えるいくつもの課題を解決するのがパートタイム労働法施行の目的と言えるでしょう。
短時間労働者をめぐる課題とは?
短時間労働者をめぐる課題とはどのような内容なのでしょうか。具体的には、以下の6つが挙げられます。
①働き・貢献に見合った公正な待遇の確保
②明確な労働条件等の設定・提示
③納得性の向上
④通常の労働者への転換を始めとするキャリアアップ
⑤法の履行確保
⑥その他労働関係法令の遵守
上記6つの課題の中で特に分かりにくいと感じるのは、③「納得性の向上」でしょうか。これは、通常の(短時間労働者でない)労働者との待遇の違いやその理由について、雇用主から納得のいく説明が受けられるようにすることです。
⑤「法の履行確保」とは、短時間労働を選択することによって不合理な扱いを受けることがないよう、違法行為に対する法の実効性を確保する必要があることを示しています。
「パートタイム労働法」における短時間労働者
法律上の短時間労働者の定義
そもそもパートタイムの定義が曖昧で「自分はパート?アルバイト?」と理解していない方も多くいます。ここでは法の観点から短時間労働者の定義を確認していきましょう。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者のことを表します。
短時間労働者への雇用管理・待遇などについて定めている「パートタイム労働法(短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理改善等に関する法律)」によると、短時間労働者は
とされています。つまり、「パート」「パートタイマー」や「アルバイト」「臨時社員」「準社員」「嘱託」など、社により呼び方が異なっいても、この条件を満たせばパートタイム労働法上では”短時間労働者=パートタイム労働者”となります。
参考までに「事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいないケース」を紹介します。このケースの場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいればその労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。
◆平成29年4月から健康保険・厚生年金の適用対象の拡大に
ちなみに、「短時間労働者=社会保険加入しない人」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
平成29年4月から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大がありました。それによりこれら短時間労働者も、雇用保険・社会保険(原則501人以上の企業)に加入する条件を満たすようになっています。
その他にも、短時間労働者に対して求められる対応があります。こちらの記事から併せてご確認ください。
<参照>パートタイムとは/厚生労働省
割増賃金や各種保険法も要件を満たせば適用
パートタイムで働く場合でも、原則として通常の労働者と同じように労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害/補償保険法、男女雇用機会均等法などの労働者保護法令が適用されます。
もちろん、法定労働時間を超えて時間外労働をさせれば割増賃金の支払が必要です。
ただし、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法は、パートタイム労働者がその要件を満たしていれば適用されます。条件については次項で詳しく説明していきます。
短時間労働者を雇用する際に留意すべきポイント
パートタイム労働法と短時間労働者の定義を踏まえた上で、雇用側はどのようなことに留意すれば良いのでしょうか。まずは、自社で短期労働者及び有期雇用者を雇っているかどうかを確認しなければなりません。
短時間労働者を雇っているのであれば、留意する点は大きく分けると主に2つです。本項では、短時間労働者を雇用する際に気をつけたいポイントを2点解説いたします。
正社員と短時間労働者の待遇に差があれば理由を説明する
パートタイム労働法では、雇用形態の違いによる不合理な格差を設けることを禁止しています。そのため、もし待遇に違いがある場合には、合理的な理由を説明する責任があります。
まずは、正社員と短時間労働者の待遇に違いがないかを確認し、待遇差がある場合はその理由を明確に説明できるようにしておきましょう。
待遇の差が不合理なものであれば改善する
正社員と短時間労働者の待遇に不合理な格差が設けられていることを確認した場合は、速やかに改善する必要があります。
就業規則を改正する場合には、就業規則の変更が従業員に不利益を及ぼさないよう注意しましょう。就業規則の不利益変更は原則禁止されているので、合理的理由を根拠に変更を行うことが大切です。
▶アルバイト・パートの平均時給調査レポートはこちらから
「社会保険」における短時間労働者の要件
社会保険加入条件
現在の法律では、被保険者が務める企業の従業員数により定義の違いがあります。
被保険者数が常時501人以上の企業の場合
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方
1.週の所定労働時間が 20 時間以上であること
2.雇用期間が 1 年以上見込まれること
3.賃金の月額が 8.8 万円以上であること
4.学生でないこと
被保険者数が常時500人以下の企業の場合
(ア)労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)
または
(イ)地方公共団体に属する事業所
いずれかに該当し、
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、 以下 の①~④全て の要件に該当する方
1.週の所定労働時間が 20 時間以上であること
2.雇用期間が 1 年以上見込まれること
3.賃金の月額が 8.8 万円以上であること
4.学生でないこと
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に定められている労働者個人が勤務すべき時間のことです。パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、契約書上の就業時間が週20時間以上かつ30時間未満で他3項目も該当する場合、社会保険の適用対象となります。
また「雇用期間が1年以上見込まれること」という部分について、雇用期間が1年未満であっても雇用契約書に契約が更新される、または更新される可能性があると記載されていたり、同様の雇用契約で働いている従業員が1年以上雇用されている実績がある場合、1年以上の雇用期間継続が見込まれるとされ加入対象となります。
扶養にもかかわるため、特にパートで働く人にとって賃金月額は重要視されます。ここでの8.8万円には、慶弔手当や賞与、時間外労働などの割増分の賃金、通勤手当、家族手当、勤続手当は含まれません。
平成28年の厚生年金保険法や健康保険法の法改正前は、「1週間の所定労働時間または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者(=正社員)の4分の3未満である」とされており、この基準は「4分の3基準」と呼ばれていました。
正社員の週所定労働時間は40時間のことが多いため、一般的には週所定労働時間が30時間を下回る場合に短時間労働者に該当しました。
<参照>短時間労働者の社会保険加入要件/厚生労働省・日本年金機構
▶アルバイト・パートの平均時給調査レポートはこちらから
「雇用保険」における短時間労働者の要件
では、雇用保険の加入条件はどのようになっているのでしょうか。
雇用保険加入条件
短時間労働者およびパートタイム労働者も、厚生労働省が定めている適用基準のいずれにも該当するときは雇用保険の被保険者となります。その基準とは次の2つ。
1.仕事開始から最低でも31日以上働く見込みがあること
2.週の労働時間が20時間以上であること
事業主は雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所に届け出を行いましょう。
この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。
2022年10月と2024年10月に社会保険の適用対象が拡大
2020年5月末に年金制度改正法が成立しました。この改正により、2022年度と2024年度の二度にわたって社会保険の定期用範囲が変更になるため、企業側はぜひ確認しておきたいポイントです。
なぜ対象を広げるのか?
現在の日本は少子高齢化が進み社会保障費が増加する一方、労働者が減少する負のスパイラルに陥っています。
そのためこれまでは短時間労働者として扶養内で働いていた主婦・主夫や、まだまだ働ける高齢者が働きやすいシステムを作り、働き方の多様化を促進するねらいがあります。
具体的な変化は?
今回の法改正では、これから詳細を解説する「被用者保険の適用拡大」のほかにも、
・在職中の年金受給の在り方の見直し
・受給開始時期の選択肢の拡大
・確定拠出年金の加入可能要件の見直し
の3つの働きかけが加わります。
2022年10月にはどう変わる?
これまではパートなどの短時間労働者を厚生年金に加入させる義務を負うのは、先述の通り従業員「501人以上」規模の企業のみです。
しかし2022年10月からは基準が変わり、「101人以上」の企業が対象になります。
これまでは大手と呼ばれる企業が対象だったため、これから対象となる中小企業はぜひ詳細を確認しておきましょう。
2024年10月にはどう変わる?
2024年10月からは「51人以上」の企業にも、短時間労働者を厚生年金に加入させる義務が生じます。
なお、法改正の詳細はこちらの記事で解説していますのでご覧ください。
法改正によって女性の活躍機会が高まる
法改正により、これまでは「短時間で家庭に影響がない程度に働こう」と考えていた主婦・主夫にとっても、活躍できるチャンスが広がります。
さらに人口減少による働き手不足には主婦・主夫や高齢者の力が必要不可欠です。
企業にとって社会保険料の負担は増える課題はありますが、その分これまでの制度によって隠れていた貴重な人材を手に入れるチャンスを得られます。
最後に
短時間労働者はフルタイムで働く正社員と大きく異なる点があり、それを認識しなくてはならないのと同時に、差別なく雇用・管理していかなければならないことも忘れてはなりません。
また、最近まで短時間労働者を取り巻く労働法は改正が続きました。チェックを怠ると気付いたら労働法違反をしていた…となってしまうことも。ぜひ気を付けながら、短時間労働者を活用していきましょう。
パート・アルバイト採用なら短期間で多くの応募が集まる「しゅふJOB」がおすすめです!
年間900万人を越える求職者が「しゅふJOB」に訪問しており、低コストで求人募集を開始することが可能です。
⇒「しゅふJOBサービス・料金表資料」を無料ダウンロードはこちら
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/