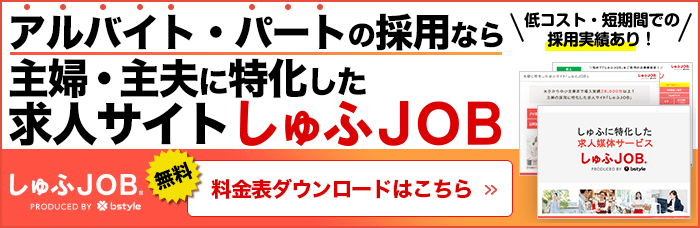法律関連
パワーハラスメント対策がの義務化|防止法や罰則についてご紹介
- 更新日:
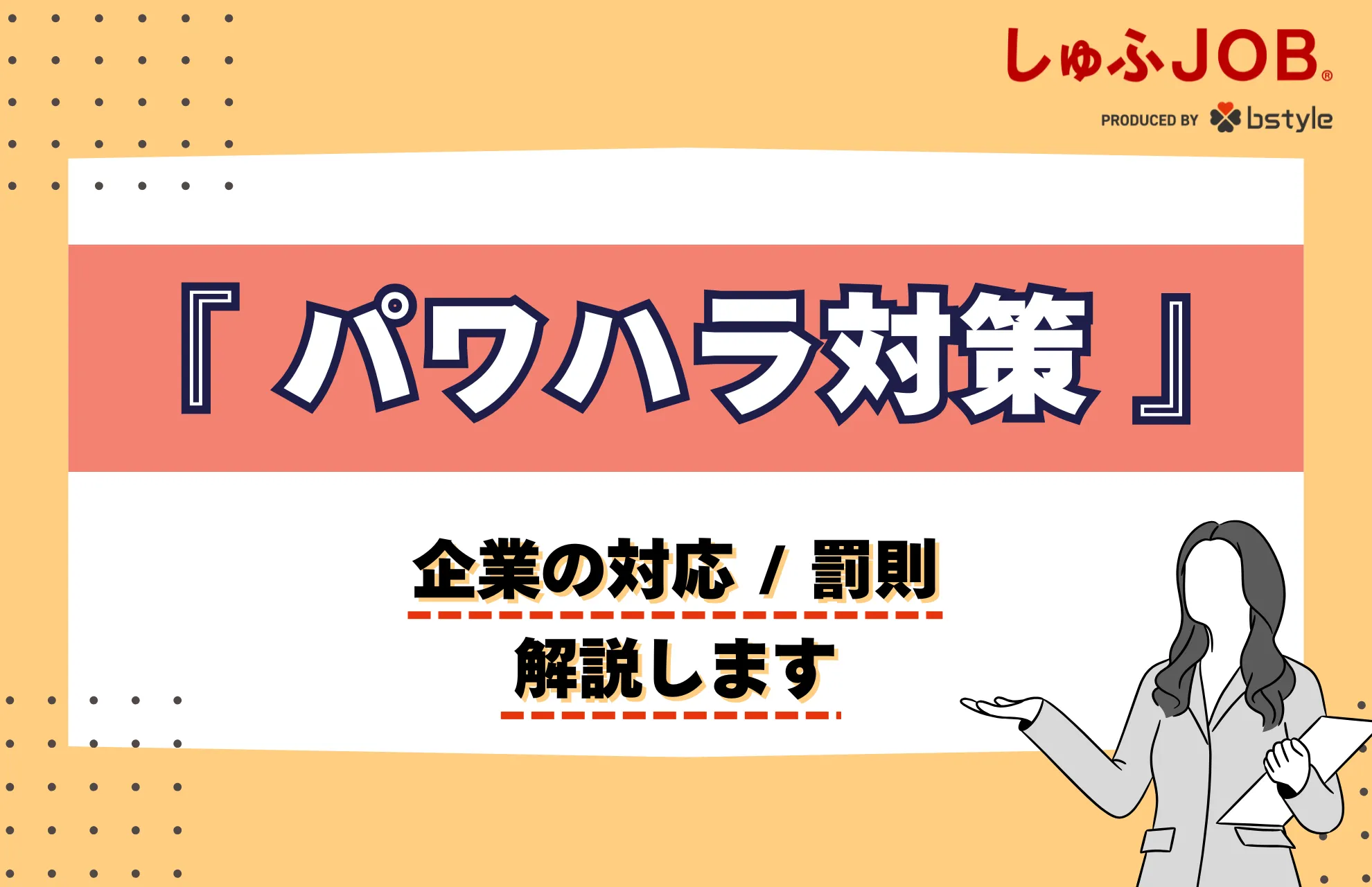
主婦・主夫に専門特化した「しゅふJOB」
企業成長に必要なパート人材を採用しませんか。
年間1000万人以上が集まり、導入企業様数2万社以上の”主婦・主夫採用”に特化した
求人媒体しゅふJOB。
NHKをはじめ日経新聞、雑誌などにも多く取り上げていただき、
また革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞」において
「厚生労働大臣賞」を受賞しました。
しゅふJOBでは、プロのライターが求人原稿作成を無料支援。
人材に合った最適な求人原稿を、カンタンですぐに掲載できます。
また掲載課金だと1週間12,000円~で即採用も可能!
費用対効果が高くお客様にご好評いただいているプランになります。
<ご利用企業様のお声>
「応募数、求職者の就業意欲に満足!他媒体に比べ圧倒的に応募が多い」
「学生より主婦・主夫層の応募が欲しい、そんな時しゅふJOBが解決してくれた」
「法律関連の情報もすぐに発信してくれて助かる」
まずはお気軽にホームページをご覧ください。

この記事の監修者
石橋聖文
人気の記事
-

しゅふJOB・メソッド
求人募集しても人が来ない会社とは?3つの原因と応募を増やす方法を解説
求人を募集をしているのに人が来ない会社とは?採用担当者が気になる点ではないでしょうか。 求人広…
-
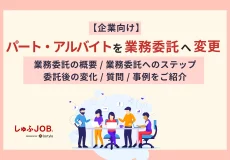
しゅふJOB・メソッド
【企業向け】パート・アルバイトを業務委託に変更した事例をご紹介
2020年は新型コロナ感染拡大を受け、昨今の「働き方改革」の推進以上に、大きく変化をもたらしました。…
-

しゅふJOB・メソッド
応募課金型の求人サイトとは?メリットやデメリットを事例を交えて解説
「できるだけ無駄な費用なく採用活動を進めたい」「応募がこなくて掲載料だけとられる状況に不満がある」と…
-

しゅふJOB・メソッド
ハローワークで応募が来ない!その原因と対策、成功ノウハウをご紹介
ハローワークは企業にとっては広告費がかからないため採用活動において強い味方です。 求職者が失業…
-

しゅふJOB・メソッド
しゅふJOB|企業様向け管理サイトのログイン方法
この記事ではしゅふJOB 管理サイトの具体的な活用方法を紹介いたします。 掲載4日で10名の応…
-

しゅふJOB・メソッド
テレアポ業務・カスタマーサポートセンターを完全リモート化!成功事例
新型コロナをきっかけに様々な業務のリモートワーク化が急速に進みました。ですがリモートワーク化が難しい…
-
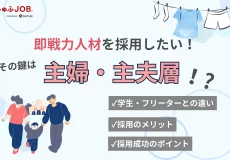
採用方法
即戦力人材の採用、その鍵は『主婦・主夫層』?│採用メリットを解説<パート・アルバイト>
パート・アルバイトで即戦力採用を行いたいが、売り手市場の昨今、自社が求める希望の人材からの応募を集め…
-

しゅふJOB・メソッド
新人研修も完全オンラインで!内容・メリット/デメリット・注意点は?参加した新入社員、上司の感想をご紹介します
2020年4月、求人サイト「しゅふJOB」運営元である、株式会社ビースタイルメディアには4名の新入社…
-

しゅふJOB・メソッド
検索ワード1位の「在宅」|勤怠の安定した在宅スタッフの活用術を解説
主婦/主夫採用に特化した求人媒体「しゅふJOB」のフリーワード検索の一位は常に「在宅」。 この…





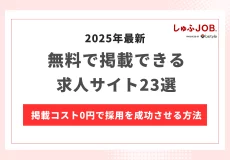
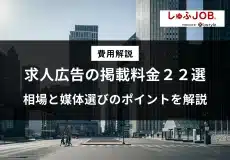
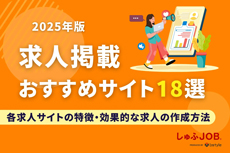
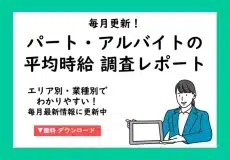
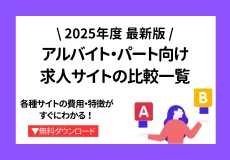
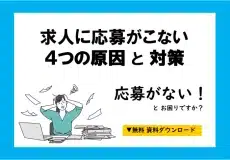

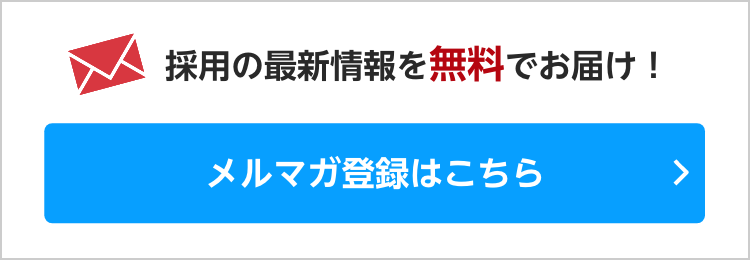
職場内でのパワハラが身近な話題として取り上げられるようになっているため、パワハラ防止法という名称に聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか。
しかし身近な話題やニュースなどで聞いたことはあっても、その定義や実態を詳しく理解している人は少ないかもしれません。
そこで本記事では、パワハラの定義やパワハラ防止法の概要について、わかりやすく解説していきます。「知らなかった」では済まされない問題ですので、ぜひこの機会に正しい理解を深めていただければ幸いです。
また、同法が成立するに至った経緯やその目的について正しく理解することで、この問題にいかに向き合えば良いのかが明らかになるでしょう。
掲載4日で10名の応募実績!求人サイト「しゅふJOB」の資料をダウンロードする
【目次】
「パワハラ防止法」とは?
パワハラ防止法は、労働施策総合推進法の通称です。同法自体は1966年に「雇用対策法」として制定されましたが、働き方改革推進の流れの中で2018年に改称されました。
この法律は、職場での悩みに関する相談で件数の多い、立場の違いを背景とした問題を予防・解決することを目的としています。
罰則規定はありませんが、パワハラ対策が法制化されることにより、世間の関心がさらに高まる効果は大きいでしょう。
さらに、パワハラに対する理解を深める効果も見込めるため、同問題の相談をしやすくなる風潮にもつながるものと考えられます。
2022年4月から中小企業も対象に
2020年6月に、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題」への対策が大企業に対して義務化されました。さらに2022年4月からは、義務化の対象範囲が中小企業にまで拡大されます。
中小企業の定義は中小企業基本法により、以下のように定められています。
または常時使用する従業員の数
出典:労働施策総合推進法の改正 (パワハラ防止対策義務化)について
「パワハラ」の定義とは?
パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とする言動によって、他人の精神や身体に害を与えることです。
つまり職場において逆らうことが困難な立場の人を、不当に苦しめる行為をすることと考えて良いでしょう。
ではどのような要件を満たしているケースで問題とみなされるのか、そして対象となり得る具体的な行為とはどういったものでしょうか。
ここではパワハラの3要素と、代表的な言動の6類型について解説致します。
3つの要件
厚生労働省は以下の3つを要件として定めています。
①優越的な関係を背景とした言動
会社やチームで業務を行うにあたって、受け手が逆らえない可能性が高い関係における言動です。
上司や先輩から部下や後輩に対する言動はもちろんですが、同僚や部下からであっても、業務の円滑な遂行を妨げるようなケースでも「優越的な関係」とみなされます。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
一般的な常識から考えて、明らかに業務上不必要である言動や、その場にふさわしくない言動を指します。
③労働者の就業環境が害される言動
常識的に考えて、その言動により対象となる労働者が苦しめられ、職場の環境が不快なものになるようなときも該当する要件となり得ます。
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/
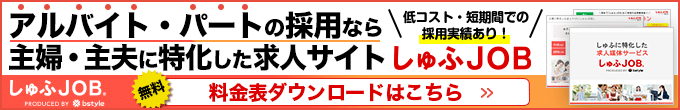
6種類の分類
問題となり得る以下の代表的な6種類の言動についても解説致します。
①身体的な攻撃
殴る・蹴る・物を投げつけるなど、直接的な暴力はもちろん優越的な関係に起因する問題行動となります。
ハラスメントにあたらない例としては、仕事中に誤ってぶつかってしまったり、怪我をさせてしまったりしたときなどがあります。
②精神的な攻撃
相手の人格を貶めたり、無駄に長い時間にわたって激しく叱責したりするなどは、精神に対する攻撃とみなされます。
相手の性自認に対する侮辱的な発言なども精神的な苦痛を与える行為に含まれるほか、必要以上に罵倒するようなメールを送ることなども含まれます。
③人間関係からの切り離し
特定の人物を無視したり、気に入らない人物をチームから外したりすることはパワハラにあたります。また長期間にわたって孤立して作業をさせることも人間関係からの切り離しと考えられるでしょう。
④過大な要求
対応できないほどの無理な業務を課し、達成できなかった際に罵倒・叱責するなどの行為がこれにあたります。
また、業務とは無関係な雑用を強いることも過大な要求に含まれるでしょう。
⑤過小な要求
嫌がらせを目的として、能力に見合わない簡単な作業だけを行わせることは、過小な要求であるとみなされます。精神的苦痛を与えることを目的として、タスクを与えないことも同様です。
⑥個の侵害
職場以外での私的な行動に対して、業務上の必要を超えたレベルで干渉することは、個の侵害にあたります。
労働者の病歴や性的指向・性自認などの個人情報を、本人の承諾を得ずに吹聴することも個の侵害にあたります。
パワハラの具体例
暴力や精神的攻撃など、加害者側に悪意がある場合には、嫌がらせであると判断することはさほど難しくないでしょう。しかし実際に職場で当該行為があったか否かを判断する場合には、受け手の感じ方が大きな比重を占めます。
例えば具体的な例として、部下を叱責するときに「相変わらずバカだなあ」や「本当に使えないやつだなあ」などと笑いながら言ってくる上司などがいるとします。
多くの部下は上司のこのような口調に慣れていて、さほど悪意のある言動であるとはとらえていません。
しかし新入社員の中に、上司の表現に苦痛を感じ悩んでいる社員がいた場合にはどうでしょうか。この場合は、精神的な攻撃とみなされてしまうでしょう。
発言した本人に悪意がない場合でも、言われた側が苦痛を感じるケースもあるということを、常に頭に入れておくべきなのです。
企業に義務付けられることは?
2022年5月現在では、大企業に続き、中小企業にもハラスメント対策を講じることが義務付けられています。
ではハラスメントを防止するために、企業に求められている対策とはどのようなものなのでしょうか。
大きく分けると以下の3点となります。
・相談窓口および適切に対応するために必要な体制の整備
・社内方針が十分に周知される体制の整備
・パワハラ発生時の適切な対応体制の整備
それでは次に、それぞれの具体的な内容について詳しく解説致します。
相談窓口および適切に対応するために必要な体制の整備
嫌がらせ・いじめ行為を受けている場合や、職場でハラスメントが生じていると思われる場合に相談できる窓口を設けることが必要です。
相談窓口を設けるだけでなく、窓口の存在を職場の人たちに広く知らせることも義務付けられています。窓口だけを定めていても、その存在が隠されていたり、皆に知られていなかったりしては意味がないからです。
また、受けた相談に対してケースごとに的確な対処を行えるように、ガイドライン作成や研修制度の充実をはかる必要もあります。
さらに、相談・報告があった際には、事実関係の調査・確認をして迅速に対応するといったスピードも求められるでしょう。職場でのハラスメント問題に対する一連の対応には、社内での意思統一も不可欠となります。
社内方針が十分に周知される体制の整備
問題となり得る言動の内容を明確化し、社内で共有することも必要です。その上で、疑われるような行為をしないよう、職場の人たちに周知・啓発しなくてはなりません。
問題となり得る言動の内容や、ハラスメント行為に対する罰則規定も就業規則などに明文化することも重要となります。
つまり会社としてパワハラに対しどう向き合うのか、そしてパワハラを行った場合にはどのような処罰があるのかが十分に周知される体制を整えなければならないのです。
また定期的に講習会を行うことや、パンフレットの配布・ウェブサイトへの方針記載なども必要となります。
パワハラ発生時の適切な対応体制の整備
パワハラが発生してしまったときに、会社が行うべき対応は以下のようなものです。
・事実関係を速やかに正しく確認すること
・行為者に適正な措置を行うこと
・被害者に適切な配慮を行うこと
・再発防止に向けた対策を講じること
上記の対応は、たとえ問題が発生した事実が確認されなかった場合でも、同様の措置を講じなければなりません。
さらに、相談者・行為者などのプライバシーを保護するための対策を整備し、それを社内で周知させることも必要です。
相談をしたことが原因で不利益を被ることや、疑いがあるだけの段階で「加害者」の扱いを受けることがないよう、対応には細心の注意が求められます。
まとめ
大企業だけでなく、中小企業でも適切な対策をすることが義務付けられました。対策を講じることに消極的だった企業にとっては、今回の義務化が不利なものととらえられるかもしれません。
しかしさまざまなハラスメント問題は、自分とは関係ないところで起こるものではありません。職場環境を良好なものに保ち、不安なく働くために、パワハラ対策は必須であるはずです。
パワハラ防止法の具体的な内容を理解することで、被害者・加害者になる可能性を低くすることができるでしょう。本記事がその一助を担えることを願っています。
時流に沿って新たに加わる「法」や「法改定」について、詳細な内容や実態をすぐに把握することは簡単な事ではありません。しゅふ採用専門の「しゅふJOB」は、当記事のように必要な情報を分かりやすく発信しています。ぜひ、しゅふ採用をご検討ください。
⇒「しゅふJOBサービス・料金表資料」を無料ダウンロード
参考:パワハラの判断基準とは?|具体例や対処法について解説|ベンナビ
参考:「パワハラ」を生じさせてしまうリスクのある心理作用『スケープゴート』とは!?|株式会社SBSマーケティング
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/