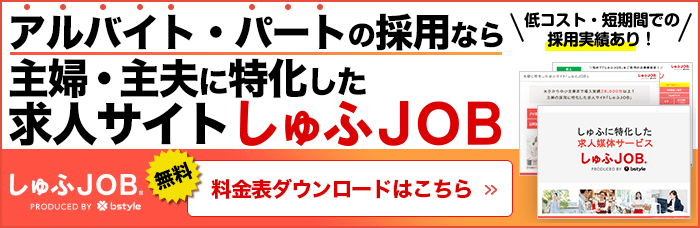法律関連
【2024年版】社会保険の法改正|従業員数の数え方や注意点を解説
- 更新日:

主婦/主夫に専門特化した「しゅふJOB」
企業成長に必要なパート人材を採用しませんか。
年間1000万人以上が集まり、導入企業様数2万社以上の”主婦/主夫採用”に特化した
求人媒体しゅふJOB。
NHKをはじめ日経新聞、雑誌などにも多く取り上げていただき、
また革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞」において
「厚生労働大臣賞」を受賞しました。
しゅふJOBでは、プロのライターが求人原稿作成を無料支援。
人材に合った最適な求人原稿を、カンタンですぐに掲載できます。
また掲載課金だと1週間12,000円~で即採用も可能!
費用対効果が高くお客様にご好評いただいているプランになります。
<ご利用企業様のお声>
「応募数、求職者の就業意欲に満足!他媒体に比べ圧倒的に応募が多い」
「学生より主婦/主夫層の応募が欲しい、そんな時しゅふJOBが解決してくれた」
「法律関連の情報もすぐに発信してくれて助かる」
まずはお気軽にホームページをご覧ください。
人気の記事
-

しゅふJOB・メソッド
求人募集しても人が来ない会社とは?3つの原因と応募を増やす方法を解説
求人を募集をしているのに人が来ない会社とは?採用担当者が気になる点ではないでしょうか。 求人広…
-
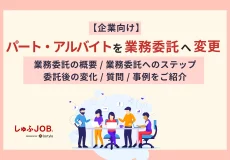
しゅふJOB・メソッド
【企業向け】パート・アルバイトを業務委託に変更した事例をご紹介
2020年は新型コロナ感染拡大を受け、昨今の「働き方改革」の推進以上に、大きく変化をもたらしました。…
-

しゅふJOB・メソッド
応募課金型の求人サイトとは?メリットやデメリットを事例を交えて解説
「できるだけ無駄な費用なく採用活動を進めたい」「応募がこなくて掲載料だけとられる状況に不満がある」と…
-

しゅふJOB・メソッド
ハローワークで応募が来ない!その原因と対策、成功ノウハウをご紹介
ハローワークは企業にとっては広告費がかからないため採用活動において強い味方です。 求職者が失業…
-

しゅふJOB・メソッド
しゅふJOB|企業様向け管理サイトのログイン方法
この記事ではしゅふJOB 管理サイトの具体的な活用方法を紹介いたします。 掲載4日で10名の応…
-

しゅふJOB・メソッド
テレアポ業務・カスタマーサポートセンターを完全リモート化!成功事例
新型コロナをきっかけに様々な業務のリモートワーク化が急速に進みました。ですがリモートワーク化が難しい…
-
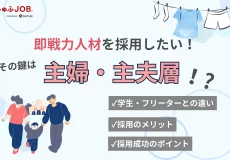
採用方法
即戦力人材の採用、その鍵は『主婦・主夫層』?│採用メリットを解説<パート・アルバイト>
パート・アルバイトで即戦力採用を行いたいが、売り手市場の昨今、自社が求める希望の人材からの応募を集め…
-

しゅふJOB・メソッド
新人研修も完全オンラインで!内容・メリット/デメリット・注意点は?参加した新入社員、上司の感想をご紹介します
2020年4月、求人サイト「しゅふJOB」運営元である、株式会社ビースタイルメディアには4名の新入社…
-

しゅふJOB・メソッド
検索ワード1位の「在宅」|勤怠の安定した在宅スタッフの活用術を解説
主婦/主夫採用に特化した求人媒体「しゅふJOB」のフリーワード検索の一位は常に「在宅」。 この…




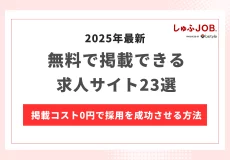
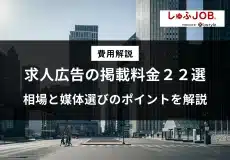
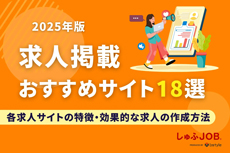
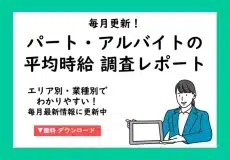
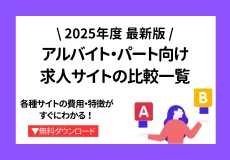
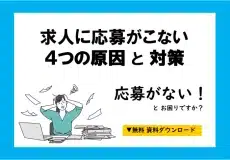

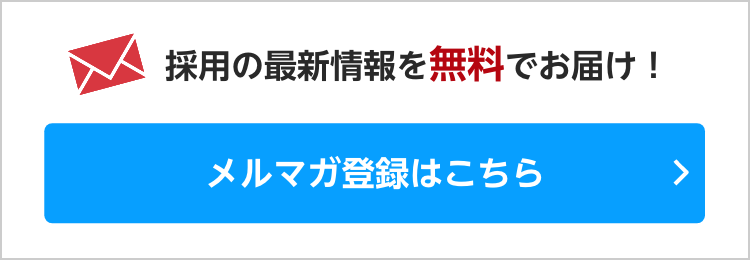
2020年に成立した年金制度改正法により、社会保険の対象範囲が段階的に拡大され、この流れは2024年まで続いています。特に2022年10月の社会保険適用拡大は、パート・アルバイトの働き方に大きな影響をもたらしました。新たな法改正により、パート・アルバイトの採用にはどのような影響があるのでしょうか。
本記事で詳しく解説するのは、この法改正の適用範囲や働く人々への影響やメリットについてです。さらに2023年度・2024年度の新たな変更点にも注目し、採用・人事に適切に対応できるような情報提供を心がけます。
掲載4日で10名の応募実績!求人サイト「しゅふJOB」の資料をダウンロードする
【目次】
【2022年10月】社会保険の法改正ポイントとは?
2016年10月の法改正により、すでに従業員501人以上の企業で働くパート・アルバイトの方は社会保険加入の対象となっています。
今回の法改正では2022年10月から、次に2024年10月から段階的に適用範囲が拡大されることが決定しています。
本項では、社会保険の適用拡大について具体的に変更されるポイントを解説いたします。
(1)対象となる勤め先の規模が変わる
2022年7月現在、社会保険加入の対象者は常時501人以上の従業員を雇っている会社に勤めている人となっています。
2022年10月より、対象となる勤め先の規模が従業員数常時101人以上の事業所へと変更されます。さらに2024年には、この規模が従業員数常時51人以上の事業所へと変更される予定です。
従業員数の「常時101人以上」や「常時51人以上」というのは、事業所で働いている人の数ではない点には注意が必要です。
社会保険加入の要件として数えられる従業員数とは、「常時使用されている」必要があり、その事業所に所属する厚生年金被保険の適用対象者の人数となっています。
(2)加入する資格の要件が変更される
2022年7月現在、常時501人以上の従業員を雇っている事業所に勤務している人は、以下の要件を全て満たす場合に社会保険加入の対象となります。
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・1年以上の勤務見込み
・学生でないこと
2022年10月からは、上記の「1年以上の勤務見込み」という条件が「2ヶ月以上の勤務()見込み」へと緩和されます。
以下にて、2022年10月からの社会保険加入の条件をまとめていますので、現在の条件と比べて条件がどのように変化するか注目してください。
・従業員数常時101人以上の事業所に勤務
・週の所定労働時間20時間以上
・2ヶ月以上の勤務(雇用)見込み
・学生でないこと
(3)社会保険に加入できる人が増える
社会保険に加入するためのハードルを下げ、できるだけたくさんの労働者を社会保険に加入させるという動きが2016年から始動しています。
今回の法改正についても社会保険加入条件緩和の流れを受けてのものであり、さらに多くの人が社会保険に加入できるようになるでしょう。
以前は、社会保険に対して正社員やフルタイムで働く人だけが加入するものというイメージがありました。
しかし、徐々に進められてきた制度改革により、現在ではパートやアルバイトのような短時間労働者でも、条件次第で加入できるように適用範囲が広がってきているのです。
【2023年最新】社会保険の法改正内容の詳細とは?
2023年度の社会保険法改正は、パートタイムやアルバイトの労働者、そして企業にも大きな影響を与えることが予想されます。
そのため、それぞれの立場から法改正の主なポイントとその影響について把握し、適切な対策を立てることが重要です。
本章では、2023年度の社会保険法改正について、その概要と各方面への影響について詳しく解説します。
2023年法改正の概要とポイント
2023年度の主な改正点には、以下のようなものがあります。
・出産育児一時金の支給額を引き上げ
・子ども家庭庁の設立
・月60時間超の時間外労働の割増賃金率を引き上げ
・給与のデジタル払い制度の導入
・社会保険料率の改定
上記の改正は、少子化問題対策や働き方改革の推進を目的としており、従来の制度に変更をもたらします。
子育て世帯を継続的に支援するという理念に基づき、若年層の所得を増やすことや、社会全体の意識改革が重視されるでしょう。
法改正によるパート・アルバイトへの影響
2023年の法改正が、パート・アルバイトの働き方に対して、どのような影響をもたらすかを把握することは重要です。
月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げは、長時間働いている労働者の賃金アップを実現します。企業は時間外労働を抑制する方向に進む可能性があり、結果として過労の問題が減ることを期待できるでしょう。
また、給与のデジタル払い制度の導入により、電子マネーでの賃金受け取りが可能となります。時代の変化に合わせて、給与受け取り方法の選択肢は増えてきました。給与を受け取ってすぐに使える利便性と速さは、今の時代に合った方法と言えるでしょう。
法改正による企業側への影響と対策
月60時間超の時間外労働の割増賃金引き上げは、労働コスト増加を招く可能性があり、企業側への影響が大きいでしょう。企業は労働時間管理と、より効率的な業務運営に取り組むことが求められます。
また、給与のデジタル払い制度の導入により、企業は新たなシステム構築と運営に必要な知識・技術を獲得しなければなりません。
変更点に対応するために、企業側には柔軟な対応が必要となります。労働者の働き方やライフスタイルの変化に対応することで、企業はより良い労働環境を提供し、従業員の生産性も向上させられるでしょう。
社会保険料率の改定とその影響
2023年4月から社会保険料率の改定も実施されており、これは労働者と企業の双方に大きな影響を与えるでしょう。具体的には、雇用保険料と介護保険料率の引き上げが予定されています。
社会保険料率の改定は、給与からの控除額に影響を及ぼすため、手取り給与の変動を引き起こす可能性があることに注意が必要です。
企業にとっては、雇用保険料率の引き上げが、負担増大につながる可能性があります。また、介護保険料率の引き上げも、労働者の一部を介護職として雇用している場合には企業の負担増となるかもしれません。
影響を最小限に抑えるために、企業には早期の対策が求められます。労働者への的確な情報提供と経営戦略の再構築がカギとなるでしょう。
【2024年最新】2024年10月に常時使用される従業員数が51名以上の事業者も社会保険の加入対象になります
2024年10月に、「常時使用される従業員が101名以上の事業所であること」から、「常時使用される従業員が51名以上の事業所であること」に社会保険の加入対象が変更されます。
従業員数の数え方
これまで同様、社会保険加入の要件として数えられる従業員数とは、常時使用されている必要があり、その事業所に所属する厚生年金被保険対象者の人数となっています。
対象となる従業員は、以下の通りです。
・常時使用される従業員数51人以上の事業所に勤務
・週の所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・2ヶ月以上の勤務(雇用)見込み
・学生でないこと
パート・アルバイト従業員でも、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務であり、上記の5つに全て当てはまれば従業員数に含まれます。
従業員数の変動が大きい会社では、従業員数判断のタイミングに悩むかもしれません。月ごとに従業員数の増減がある場合は、「直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階」で適用対象となります。
また、適用対象となった後に、従業員数が適用従業員数を下回った場合でも、原則として引き続き適用されるので注意が必要です。
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/
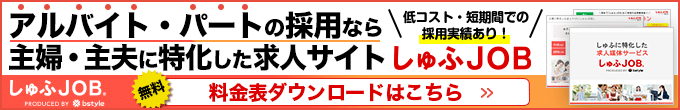
社会保険とは?
ここまで社会保険の適用拡大について解説してきましたが、そもそも社会保険についてよく分かっていないという人もいるかも知れません。そこで本項では、社会保険とは何かについて解説しておきます。
社会保険というのは、1種類の保険ではなく「健康保険」「年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」を総合した名称です。
社会保険の中でも、特に話題に上がりやすい健康保険と年金保険について解説し、加入のメリット・デメリットについても考えてみましょう。
健康保険
健康保険とは、病気やケガによって働けなくなったり、生活に困ったりすることを避けるための保険と理解しておけば良いでしょう。
健康保険の財源は、被保険者と雇用主とが分担して支払う保険料です。事故や病気などによって保険の給付が必要になると、加入者たちが支払っている保険料から給付される仕組みとなっています。
勤め先の会社で社会保険に加入するという場合には、この健康保険を指していると考えて良いでしょう。
保険料の支払いは被保険者と会社との折半であり、保険料の全額を自己負担する「国民健康保険」とは違うので注意が必要です。
年金保険
日本の公的年金制度には、20〜60歳の全ての人が対象の「国民年金」と、勤め先の会社で加入する「厚生年金」の2種類があります。
国民年金は対象となる年齢の全ての人が加入する年金であり、二階建て構造になっている年金制度の一階部分にあたります。それに対して、会社に勤めた時に加入する厚生年金は二階部分に相当します。
本記事で解説している社会保険で年金保険という場合は、国民年金ではなく厚生年金のことを意味しています。厚生年金の保険料は、健康保険料と同様に被保険者と事業主との折半となります。保険料を全額負担する国民年金との違いも押さえておきましょう。
社会保険加入のメリットやデメリットとは?
社会保険に加入することで、どのような恩恵を受けることができるのでしょうか。
本項では、加入のメリットに加えてデメリットも解説いたします。
社会保険加入のメリット
社会保険に加入することのメリットは、将来支給される年金の額が増え、種々の手当金・一時金などを受給できる点です。
老後に備えて年金の額を増やしておきたいと考える人にとって、社会保険加入のメリットは大きいでしょう。
社会保険に加入するのを前提として働いている人であれば、収入調整に気を使う必要がない点もメリットとなるはずです。
社会保険加入のデメリット
収入額によっては、社会保険に加入することで負担金額が増えてしまうデメリットがあります。いわゆる「106万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか?
年収が106万円を超えると、条件次第で社会保険に加入することになります。しかし、収入が106万円を少しだけ超える場合には、保険料の支払いにより手取り金額が減ってしまうことで損をしたと感じる人もいるでしょう。
収入をうまく調整しなければ、長時間働いたのに手取りが減ってしまう可能性があります。それでも将来の年金が増えることなども考えると、完全なデメリットとは言えません。
⇒「しゅふJOBサービス・料金表資料」を無料ダウンロード
社会保険加入に関する注意点
法改正により社会保険加入者が大幅に増えると、制度についてよく理解できていないケースも増えてくるでしょう。
ここでは社会保険に加入する場合に、注意しておくべきポイントについて解説いたします。思わぬところで失敗することがないように、ぜひ参考にしてください。
条件を満たす場合は強制加入
社会保険の加入条件を満たしている場合でも、手取り収入が少なくなるなどの理由で、加入をしたくないという場合はあるでしょう。そのような場合に、社会保険加入を拒否することは可能なのでしょうか。結論から言うと「ノー」です。
要件を満たしている場合には、加入が義務付けられています。もし加入しなかった場合、事業主は刑事「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」を科せられる可能性があるので注意しましょう。
加入しなかった労働者側に罰則はありませんが、加入していなかった期間に対して最大2年間までの「さかのぼり加入」をさせられるリスクがあります。長い期間の保険料をまとめて徴収されることになると、手持ちの現金が一気に減ってしまいます。
本記事を読んでいるパートの方で、社会保険の加入条件や保険料について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
▶パートは社会保険・厚生年金で得をする? 加入条件と保険料を説明!
副業やダブルワークには注意が必要
副業やダブルワークで複数の会社に勤めているという場合は、どの会社の社会保険に加入するのかという問題があります。
複数の会社で重複して加入してしまった場合には、訂正手続きなどに時間と手間を取られてしまいます。いくつかの仕事を掛け持ちしている人は、どの会社で社会保険に入っているのかを把握し、他の会社にも掛け持ちの事実を知らせておかなければなりません。
⇒「しゅふJOB」の料金表資料を無料ダウンロード
まとめ
2022年10月から段階的に進んでいく適用拡大により、多くの短時間労働者が新たに社会保険に加入することになるでしょう。
加入者が増えるという単純な影響だけでなく、加入したくない労働者が増えたり働き方の変化が起こったりと、大きな変化が生じることが予測されます。
法改正について大まかな内容を理解しておくことで、変化に柔軟に対応することができるはずです。社会保険適用拡大について知っておくために、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
企業として法律の遵守は絶対です。法改正や新しい法の制定など、常にアンテナを張り続け守るべきルールを確認していきましょう。主婦・主夫採用に特化した求人サイト「しゅふJOB」は、本記事のように情報発信を行っています。担当者様の業務にお役立ていただければ幸いです。
⇒「しゅふJOB」の料金表資料を無料ダウンロード
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/